「やってみて判断してほしい」〜目的の見える「全力」と見えない「雑用」の間で
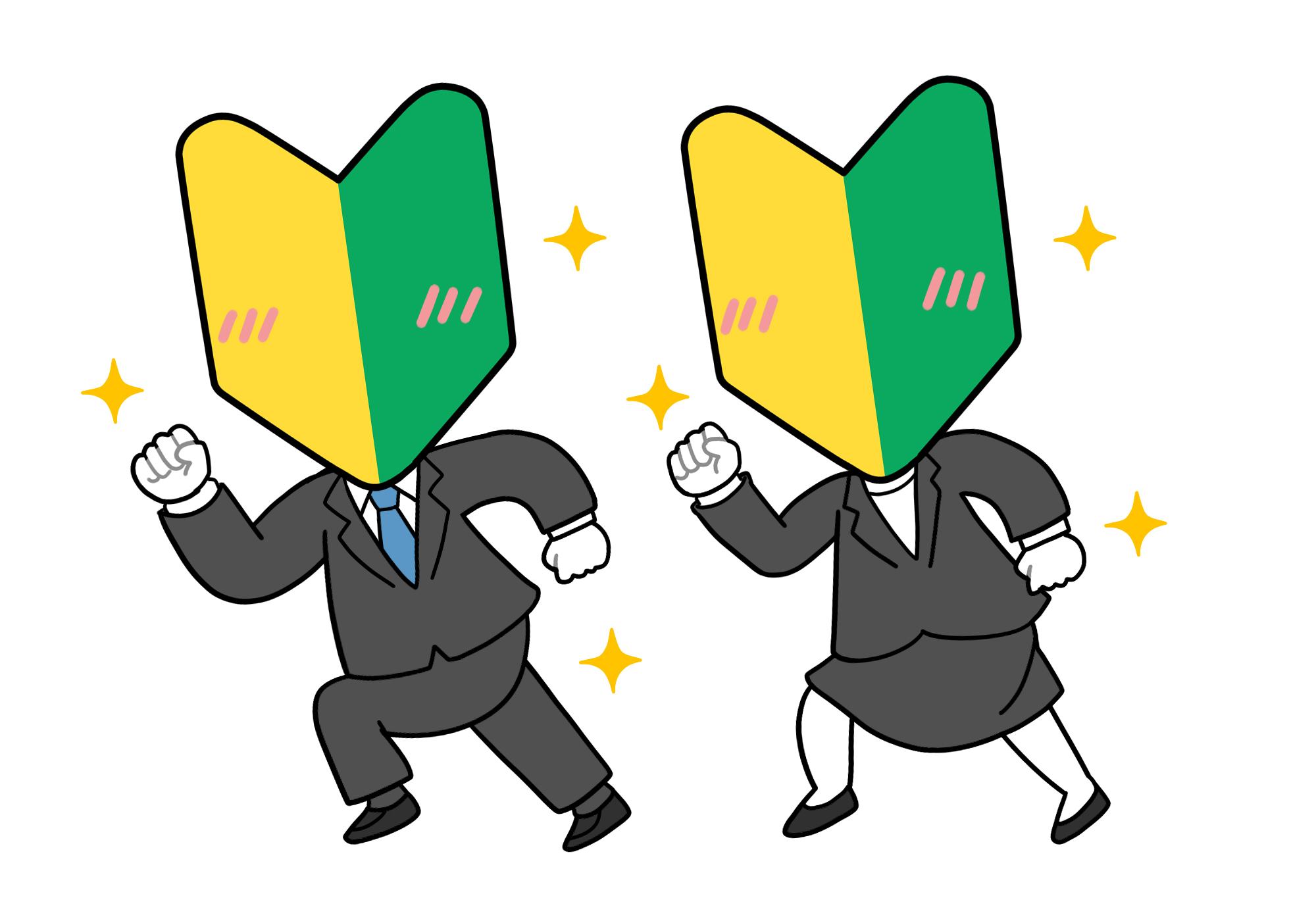
昨日、芸人のロッチ中岡さんがTV番組のロケ中に重傷を負ったニュースが報じられました。
また、パンサー尾形さんも最近、番組で愛娘の前でビンタされた件について
「バラエティーは真剣に見ないでください!!」と発信し、話題となっています。
お二人に共通するのは、「笑いを届ける」という
明確な目的に向かって全力で取り組む姿勢です。
ただ現代の日本社会では、コンプライアンスが厳しくなっていることもあり、
地上波においてどこまでが許容されるのか、現代における「全力の笑い」の難しさを示唆しています。
目的が見える「全力」の美しさ
芸人さんの「体を張る」には、明確な目的があります。
観客を笑わせたい、喜ばせたいという純粋な想いです。
だからこそ、ケガのリスクを承知で挑戦し、
結果として強い笑いや感動を生み出すことができます。
これは、目的が明確だからこそ輝く「全力」の姿です。
リスクも覚悟も、すべて「笑い」という結果に向かって意味を持ちます。
企業で直面する「意味の見えない仕事」という現実
一方、企業組織では全く異なる問題が存在します。
「自分が嫌だと思う仕事は全くやらない」
「雑用のような、やる意味がない仕事は誰がやるのか」という声です。
これは芸人さんの「全力」とは根本的に違います。
目的が見えない、なぜやるのかが分からない作業に対する疑問や抵抗感です。
特に若手の間では、自分の本当にやりたい仕事をさせてもらえる機会はまだ少ないと思います。
そのため「この作業がどう会社の目標に貢献するのか」が見えないことへの戸惑いがあります。
効率性を重視する世代にとって、意味の見えない作業は時間の無駄に感じられるのも自然です。
一方、上司の視点では、「雑用」に見える作業にも組織運営上の意味があることを知っています。
しかし、その意味を十分に伝えられていない現実があります。
「やってみて判断してほしい」が持つ二つの意味
私が提案したいのは、「やってみて判断してほしい」という考え方です。
ただし、これには二つの前提が必要です。
**1つ目は「目的の共有」です。**
芸人さんが体を張るのは、「笑いを届ける」という目的が明確だからです。
企業でも同様に、
「なぜこの作業が必要なのか」「どう会社の目標に貢献するのか」
を明確に伝える必要があります。
**2つ目は「意味の発見機会」です。**
一見無意味に見える作業でも、実際に取り組む過程で見えてくる価値があります。
資料整理から学ぶ情報の扱い方、電話応対から身につくコミュニケーション力。
これらは後に大きな財産となります。
人は心理的安全性の中でしか成長できない
現代では、「絶対に誰かが見てくれている」という言葉が
監視社会的な意味合いを持つようになりました。
だからこそ、組織には心理的安全性が不可欠です。
「意味が分からない」と言える環境、
「やってみたけれど、やはり疑問がある」と伝えられる関係性。
そしてそれを邪険にせず、一つの問題として上司が部下の気持ちに寄り添い、向き合う姿勢。
これらがあってこそ、「やってみて判断する」文化が初めて機能するのです。
まとめ
芸人さんの「目的に向かう全力」は、
『見てくれている人を笑わせたい』という心からの想いから来るものです。
一方で、企業での若手社員にとっての「意味の見えない仕事への対応」は一見全く別の問題だと思われがちです。
でも、若手社員が様々な経験をして成長し、そして本当に自分のやりたい仕事ができる時、
その時は芸人さんが思うように、「全力」で仕事に向き合えるはずです。
一見無駄な仕事に感じられても、実際に経験したことは決して無駄にならず、
むしろ自分の知識やスキルとして蓄えられ、自身の成長につながっているのです。
そのまま、ありのままの現状(As-Is)で感じる疑問を受け入れつつ、
理想の未来(To-Be)に向かって、一歩ずつ意味を見つけながら歩んでいく。
それが、現代に求められる働き方なのかもしれません。
**参考記事**:
「ロッチ」中岡さんのケガ。「パンサー」尾形さんの訴え。体を張る意味と今の時代における”全力”の難しさ


