「スーパーウーマン」を諦めた私が伝えたい、本当に必要な働き方改革
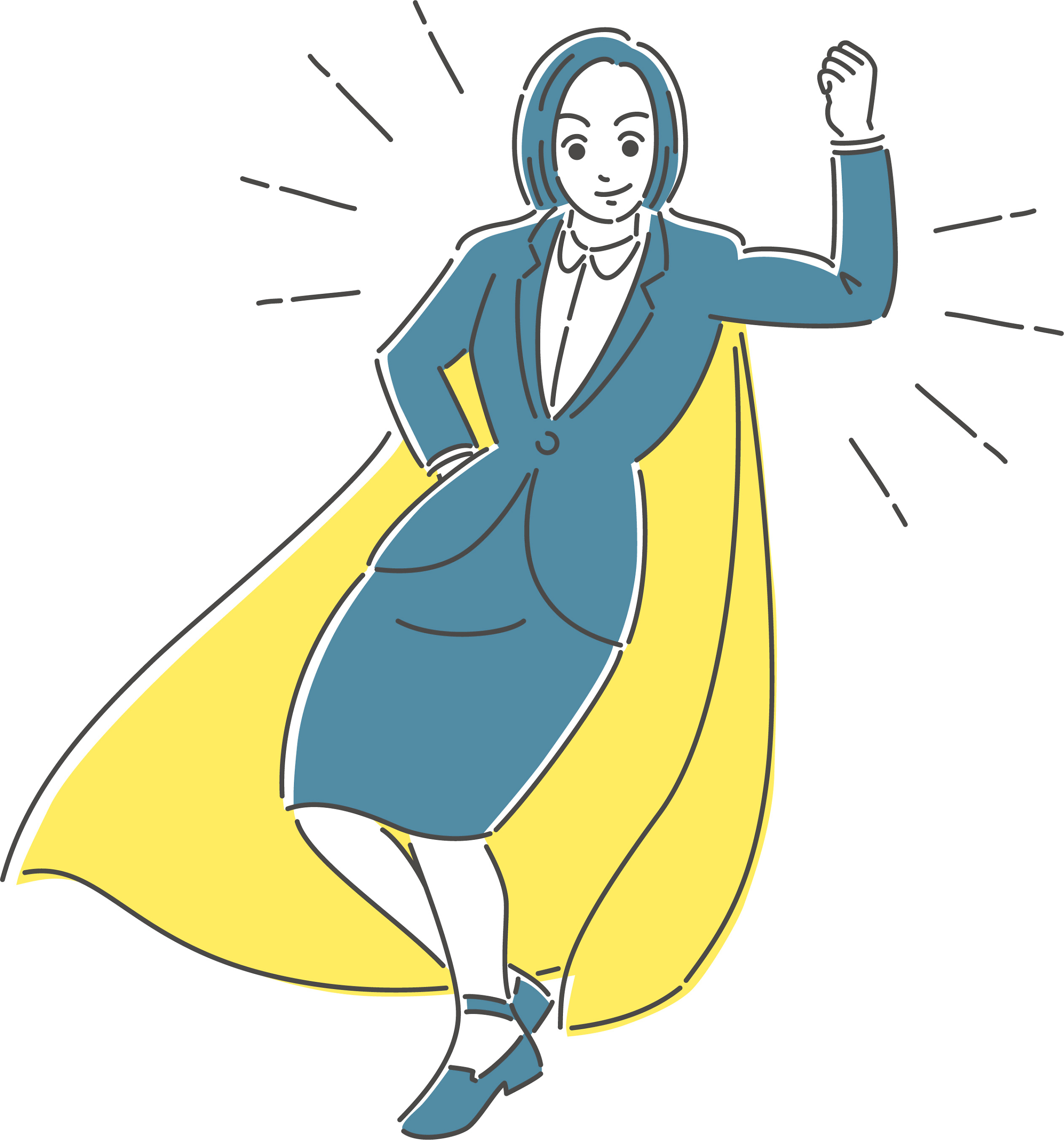
先日、日経新聞の「少子化対策の盲点」に関する記事を読み、胸が締め付けられる思いでした。
記事に登場する女性の「私は最前線に残るのを諦めただけ」「スーパーウーマンにはなれない」という言葉が、
かつての私自身の心境と重なって見えたのです。
私も長男の誕生後、家事育児と仕事の両立に必死でした。
当時はまだ今ほど家事代行サービスや育児支援サービスも充実しておらず、夫の家事育児への協力も限定的。
毎日時間に追われ、心身ともに疲れ果てていく中で、「スーパーウーマンになることを諦めた」一人でもあります。
周囲からは「うまく両立しているね」と言われることもありましたが、
内心では「何かを犠牲にしながらなんとか回しているだけ」という状況でした。
キャリアの最前線で活躍し続けたい気持ちと、母親として子どもに寄り添いたい気持ち。
その狭間で、多くの女性が苦しい選択を迫られているのが現実です。
記事にもあるように、残業前提の働き方がベースにある中、
近年でも3割の女性が第1子出産を機に退職するという状況があり、
この傾向は現在も大きく変わっていないと考えられます。
これは、私たちの社会が抱える深刻な課題を浮き彫りにしています。
単に個人の選択の問題ではなく、制度や環境の問題なのです。
そして、この課題は育児期の女性だけに限りません。
高齢化が進む日本では、今後ますます介護と仕事を両立させなければならない人が増えることが予測されます。
実際、40代・50代の働き盛りの世代が突然介護の責任を担うことになり、
キャリアを断念せざるを得ない「介護離職」も深刻な問題となっています。
このような現状を踏まえると、残業時間の上限規制だけでは根本的な解決には至りません。
必要なのは、事情を抱えた人が長く働き続けられる環境づくりです。
具体的には、短時間勤務制度の充実、フレックスタイム制度の導入、テレワークの推進、
そして何より「時間あたりの生産性」を重視する評価制度への転換が不可欠です。
「長時間働くことが美徳」という価値観から脱却し、
「限られた時間で最大の成果を出す」ことを評価する文化を醸成していく必要があります。
また、管理職や同僚の理解促進も重要です。
時短勤務の社員に対して「帰りやすくていいね」という心ない言葉ではなく、
「限られた時間で成果を出してくれてありがとう」という認識を持てるよう、組織全体の意識改革が求められます。
人的資本経営の観点からも、多様な働き方を選択できる環境は企業にとって重要な競争優位となります。
優秀な人材の離職を防ぎ、多様な経験を持つ社員が活躍できる組織こそが、変化の激しい時代を生き抜いていけるのです。
「スーパーウーマン」になることを諦めた女性たちの声は、私たちに重要な問いを投げかけています。
本当に必要なのは、『一人ひとりが無理をして頑張る』ことではなく、
『誰もが自分らしく働き続けられる』社会の仕組みづくりなのです。


